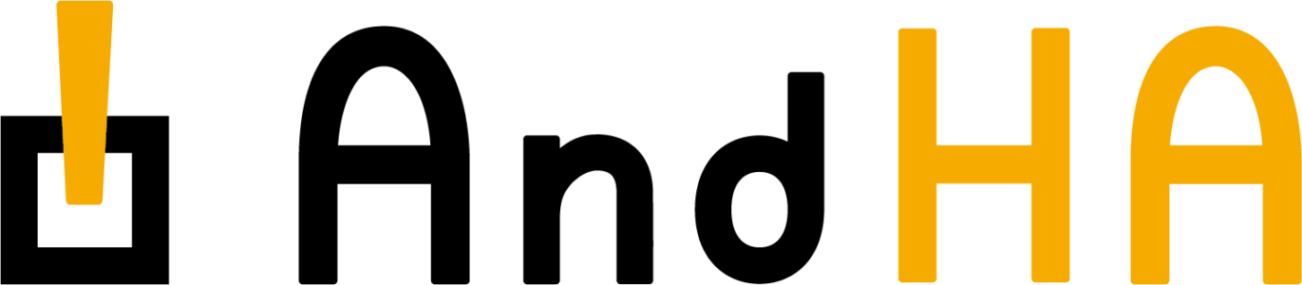04/19TUE
PEOPLE
実はこんなに幅広い!
仙台ITトップランナーに聞く
奥深きエンジニアの世界
仙台のIT業界で活躍する、ある共通点を持つ人たちに集まってもらい、食べたり飲んだりしながらざっくばらんに語り合っていただく「居酒屋INC」。
第4回目となる今回スポットを当てたのは、「エンジニア」の世界。ひと口に「エンジニア」といっても、フロントエンドからバックエンドまで様々な役割があり……「まずは何から勉強するべき?」「フロントエンドorバックエンド、転向するのは難しい?」などなど、未経験の方からするとちょっと未知数なこの業種。
これからウェブデザイナーやエンジニアを目指すIT未経験の方々と、すでにエンジニアとして活躍されている方々が、「エンジニアの世界ってどんな感じ?」と、ゆるりと居酒屋にいるような気分でお話ししてもらいました。

<参加いただいた方>
・経験者の皆さん
樋口祐紀(ひぐち・ゆうき)さん……株式会社ナナイロの執行役員、ファストエンジニアリング事業部事業部長。管理職でありながら今も日々プログラミングを組んでいるプレイングマネージャーとして活躍中。その傍ら、大学で非常勤講師として教鞭をとる
三浦崇(みうら・たかし)さん……株式会社AndHAの代表取締役。大学院在学中にものづくりの楽しさを見出し、そこからウェブの世界へ。いずれ仙台に会社を立ち上げたいという思いのもと市内に就職し、その後友人たちと起業、現在に至る
柴崎良太(しばさき・りょうた)さん……フリーランスエンジニアとして活動中。フロントエンドからバックエンドまで幅広くこなす。ここ数年は仙台の仕事も増え、地域貢献について意識するようになってきた
・未経験者の皆さん
N・Aさん……デジタルハリウッドSTUDIO仙台Webデザイナーコース専攻。前職は郵便局員
K・Sさん……デジタルハリウッドSTUDIO仙台Webデザイナーコース専攻。前職はSE。さらに深くITの世界に関わりたいと、ウェブデザインを学んでいる
G・Yさん……大学3年生でデジタルハリウッドSTUDIO仙台Webデザイナーコース専攻を卒業。大学卒業後の進路を現在模索中
どうしてITの世界に?それぞれのきっかけ

-

SENDAI INC.:未経験者の方たちが、ITの世界に興味を持ったきっかけを教えてください。
-

N・Aさん:もともと絵を描いたり、デザインしたりするのが好きだったんです。
それでウェブデザインに興味を持ちました。 -

K・Sさん:僕はSEとして働いていたんですが、プログラミングなどはほぼ未経験のまま、その上流工程である進捗管理などをしていました。
現場のことを知らないまま管理することに疑問を感じていたので、ちゃんと一から学びたいなと思ったんです。 -

SENDAI INC.:後藤さんはほかのおふたりと違い、学生さんですよね。大学に通いながら、あえてデジハリにも通おうとした理由は?
-

G・Yさん:大学は経営学部の経営学科なんですが、将来どんな道に進みたいか考えたときに「ものを作るのが好き」だなと思ったんです。
そう考えたとき、より現実的に目指せるのがウェブ上でものを作る、ウェブデザインかなと考えました。 -

SENDAI INC.:3人ともそれぞれ理由やきっかけがあってITの世界を志しているわけですね。
では、既にエンジニアとしてIT業界で活躍されている方々のきっかけは? -

三浦さん:ひと言で言うと「面白そうだな」って単純な理由なんです。
大学は工学部に入学してその後大学院まで進んだのですが、研究職はあまり向いていないなと感じまして。
わりと飽き性で新しいもの好きってところもあり、ウェブが面白そうだなって思ったのがきっかけですね。 -

柴崎さん:僕は大学では英語を勉強していたので、元は文系だったんですよね。
で、大学に通いながら福祉系のボランティアもやっていました。
ITの世界に足を踏み入れることになったきっかけは、そこで出会った人が「ITを活用して福祉をもっと良くできないか」という理念のもと、会社を立ち上げたことでした。
理念に賛同し、新卒でその会社に入社することになってすぐ「営業をやるかエンジニアをやるか選んで」って言われて。そこでエンジニアを選んだのが始まりです。
だから、エンジニアになりたくてなったわけじゃなくて、あくまで社会課題を解決するための手段としてエンジニアになりました。
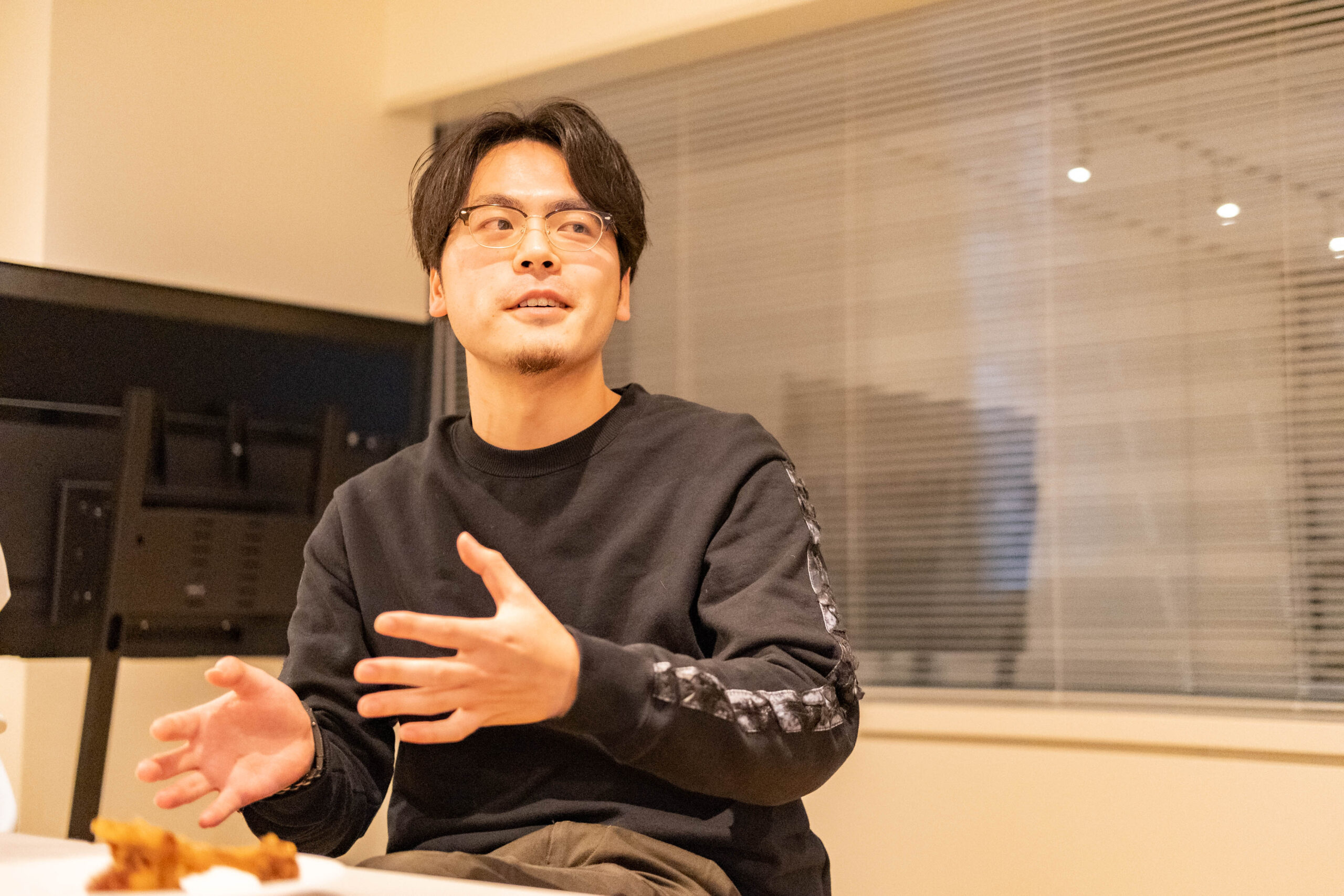
-

SENDAI INC.:おふたりとも、最初からエンジニアを目指していたわけではなかったのですね。
元々文系だった柴崎さんはとくに、未経験からの挑戦だったと思いますが、知識やスキルの修得はどのように? -

柴崎さん:僕はそれまで、Macどころかパソコンも論文を書く程度しか触ったことがなくて、正直何もできなかったんですよね。
だからその会社で働きながら勉強させてもらっていたようなものでした。HTMLやCSSを、とにかく自分で作れるところまで作る。それをがむしゃらにやりながら覚えていきました。 -

三浦さん:僕もずっと独学でしたね。人から教わったことは1度もないです。
-

SENDAI INC.:なるほど。樋口さんはなぜエンジニアの道に?
-

樋口さん:私は学生時代は教員を志望していました。
大学のソフトウェア情報学部で学びながら高校の「情報」の教員免許を取りましたし、大学院を卒業する際は他の大学のアカデミックポストを狙っていました。ですが採用まで至らなかったんです。
その後、在学中に電子黒板のシステムを作っていて元々プログラミングができたこともあって、今の会社に入社することになりました。
「フロントエンド」ってなんですか?

-

SENDAI INC.:エンジニアについてよく知らない方向けに、各業務内容について教えていただけますか?
-

三浦さん:僕がメインにやっている「フロントエンド」というのは、端的に言えばウェブサイトの見た目を整えていく作業です。
デザイン通りに表示されるようにしたり、演出と呼ばれる動きをつけたりですね。
-

SENDAI INC.:整えるというのは、具体的にはどのように?
-

三浦さん:HTMLやCSSといった言語を使ってコーディングしています。動きをつける場合は、Javascriptをよく使いますね。
-

SENDAI INC.:ウェブデザイナーとフロントエンドエンジニアはどう違うのでしょうか?どちらも見た目を整えるという印象があります。
-

三浦さん:明確な区切りはありませんが、デザインに重きを置いている人はウェブデザイナー、動きをつけたりといったコーディングに重きを置いている人はエンジニアと名乗るケースが多いのかなと思います。
「バックエンド」とは?

-

柴崎さん:フロントエンドが見た目、つまり表面に出てくる部分なのに対して、バックエンドは裏側の部分。あまり目に見えないところの作業です。
ウェブサイトで言うところのバックエンドだと、ECサイトのフォームを作ったり、ウェブ上で取得したデータを格納させるための箱のようなものを作ったりですね。 -

樋口さん:私の場合は、例えばIoT機器から集まってくる数値などのデータを貯めておくクラウド上の仕組みなどを作ったりしています。
これもバックエンドの括りになるかと思います。サービスを提供するために不可欠なITインフラを構築したり運用したりするので、「インフラエンジニア」と呼ばれたりしますね。
作りたいものによって使用言語も異なる。
奥深きエンジニアの世界
-

SENDAI INC.:「インフラエンジニア」は初めて聞きました。
エンジニアと聞くとついウェブをイメージしてしまいますが、それだけじゃないんですね。 -

柴崎さん:クライアントさんの業種だったりプロダクトの種類だったりによりけりで、エンジニアの括り方はいろいろあると思います。
ウェブサイトのバックエンドとインフラのバックエンド、やっていること自体は似ていますが、使っている言語は異なると思いますよ。

-

SENDAI INC.:エンジニアとひと口に言っても、フロントエンドやバックエンドなど役割が分かれていて、さらに同じバックエンドの中でも目的に応じて使う言語が異なるということですね。奥が深いです。
でもそうなると「まず何から勉強したらいいの?」となりませんか? -

柴崎さん:そうですね。ただ、私の場合は、「何を勉強するか」というよりも、「最終的に何を作りたいか」、「そのためには何が必要か?」ということを重視しています。
僕自身そう探求していった結果、フロントエンドもバックエンドも触れるようになっていましたし、これからも作りたいものを実現するために勉強し続けていきます。 -

三浦さん:僕はフロントエンドをメインにやっていますが、バックエンドも一通りできます。
1つのサービスを作るときに、どちらか片方だけってことは僕の経験上はなく、複数の要素が支え合ってできていますし、役割にとらわれず勉強することが大切かなと思います。
なのでエンジニアに興味がある方は、最初から「どちらか決めないと……」と構えなくて良いのではないでしょうか。実
際に作っていく過程で「自分にはフロントエンドが合ってる」「バックエンドの方が好きかな」というように、自分にとっての「メイン」が決まっていくこともありますから。
ベースの知識があれば、方向転換もできる!
ITの世界で重宝されるマインドとは
-

SENDAI INC.:例えば今までウェブサイトのバックエンドをメインにしていたけど、フロントエンドメインのエンジニアやインフラ系のエンジニアに転向したい、となった場合、それまでの経験や知識はある程度生かせるのでしょうか。
-

樋口さん:何から何への転向かにもよりますが、ものの考え方や捉え方は流用可能だと思います。
エンジニアに求められるものって、要は「プロセスを見える化する」という基本的なことで、これはずっと変わらないはずです。
逆に言えば、そういったことが得意なのがエンジニア。その根っこの部分は、次にどんなエンジニアに転向するとしても生かせると思います。 -

柴崎さん:同じ仕事を続けていく場合でも、新しいプロジェクトに入れば新たに学ぶことはたくさんありますよね。
-

三浦さん:そうですね。日々新たな技術が生まれる業界なので、エンジニアに求められるレベルも自分がこの仕事をはじめた頃と比較して高度になってきていると感じます。
-

柴崎さん:それを面白いと感じ、深掘りしていけるのが理想ですね。逆に「これは自分の領域じゃない」って線引きしてしまうと、後々つらくなる場面が出てくるかもしれません。
-

SENDAI INC.:ずっと学び続ける姿勢や根気強くついていくマインドがあれば、入り口やきっかけは何であれ、エンジニアとして長く活躍できるともいえそうですね。
-

柴崎さん:どんなお仕事にも言えますが、ベースの知識を大切に、あとはどう自分なりにインプットしていくか。自分次第で、活躍の場はどんどん広げていけると感じます。

情報は自分で取りに行く!
活躍し続けるエンジニアの勉強法
-

SENDAI INC.:エンジニアとして長く活躍するためには常に学び続けなければならないと思いますが、具体的にはどのような方法でインプットしていますか?
-

三浦さん:日々情報を追って、それを試していきます。情報はウェブや本から得ることがほとんどです。
ある程度まで本で勉強したら、あとは基本ずっとウェブですね。 -

SENDAI INC.:本やウェブを活用して知識を得る、そのうえで実際に手を動かして試してみる。
そうやって常に自身のスキルをアップデートされていると。 -

三浦さん:そうですね。簡単に情報を手に入れられる時代なこともあり、能動的に情報を取りに行って勉強しないと、一瞬で差がついてしまう業種だと思います。
個人的にデザイナーを目指すなら「最低限読むべき良書」があると考えていますが、検索するとすぐに良書の情報に出合えるので、まずは手当たり次第にでも読んでみることをオススメしますね。

-

SENDAI INC.:では、エンジニアをしていて楽しいのはどんなときですか?
-

三浦さん:作りたいものがあって、それに必要なものを学んでいく過程そのものが楽しいですし、満足したものができればすごく達成感があって嬉しいです。
-

柴崎さん:エンジニアは、一つのものを「形にしたい」とたくさんの方が関わり協力して進めてきたものを、最後に形にする役割なんです。
そこに携わっているという感覚が、満足感につながっていますね。
良いものができて、クライアントさんからもユーザーさんからも良い感想がもらえる。そういう瞬間に承認欲求がすごく満たされるんです。 -

樋口さん:承認欲求、よくわかります(笑)。私の場合はデータベースの設計をよくするんですが、検索が速く、無駄なくできるようにうまく設計できると嬉しいですね。
デザインやプログラミング、コーディングは叶えたい目標を達成するための手段のひとつ。ITの世界に興味があるけれど何から手を付けたらいいかわからないという人は、「何になりたいか」「何から勉強すべきか」ではなく、「何を作りたいか」「何を成し遂げたいか」から考えることで、目指すべき方向性が見えてきそうです。
IT業界は流れが速く、常に知識やスキルをアップデートしていく必要がありますが、その姿勢やマインドさえあればきっと大丈夫!
スキル差、案件の違い
エンジニア目線で見る仙台と東京の違い

-

SENDAI INC.:未経験者の方々は皆さん仙台にお住まいということですが、今後の働き方についてどうお考えですか?
-

N・Aさん:私は岩手出身で最近仙台に引っ越してきました。
仙台の住みやすさが気に入っているので、このまま就職したいです。 -

K・Sさん:私も仙台で就職希望です。
-

G・Yさん:私はとくに仙台にこだわりはないです。
志望している企業のなかには、本社が東京にある企業もありますし、希望の職種に就ければ場所は関係ないかなと考えています。 -

柴崎さん:僕の周りのエンジニアには、一度東京へ行ってその後地元貢献したくてUターンしてきたって人が多いですね。
-

SENDAI INC.:東京といえば……少し前からUIJターンが注目されていますが、エンジニアの視点から見て仙台と東京との差って何かありますか?
-

樋口さん:私はとくに感じたことはありません。
実際には宮城県内の会社が首都圏からの仕事を受注していることだって多いですし。
-

SENDAI INC.:スキルの差がないからこそ首都圏からの仕事ができている、と。
-

樋口さん:そうですね。ただスキルの差ではなく、案件や求められるものの差を感じることはあります。
-

SENDAI INC.:というと?
-

樋口さん:うちの会社の特徴かもしれませんが、自分たちが上流から下流までいろいろやるのに対して、
首都圏の会社は役割分担がしっかりしていて、じっくりと1つの事案なり、スキルなりに集中して対応できるイメージがあります。
どちらが良い悪いということではなく、シンプルな違いですね。

-

SENDAI INC.:優劣の差ではなく、性質の差というイメージでしょうか。
-

樋口さん:かなりメジャーなゲームタイトルの開発であっても、実は仙台など地方でやっていたりしますからね。
東京では設計や工程管理といったマネジメントを担当し、実際の開発は地方で、という構造です。 -

SENDAI INC.:そういうケースもあるのですね。
樋口さんのお話では、仙台と東京との間にスキル差はないとのことでしたが、自分なりにもっとスキルを上げたいと思った場合に何かできることはありますか? -

三浦さん:クライアントから相談を受けた際に、自分の作りたいものを提案するのは1つの手かもしれません。
自分の作りたいものが先にあると、勉強しなきゃいけないことが明確になるし、成長速度が早いんですよね。
もちろんそれが自分のエゴになっちゃいけないから、相手にとってきちんとメリットがあることが条件ですが。 -

SENDAI INC.:自分のやりたいことならクオリティもその分上がりそうですし、結果的にWin-Winかもしれませんね。
好印象を与えるポートフォリオってある?
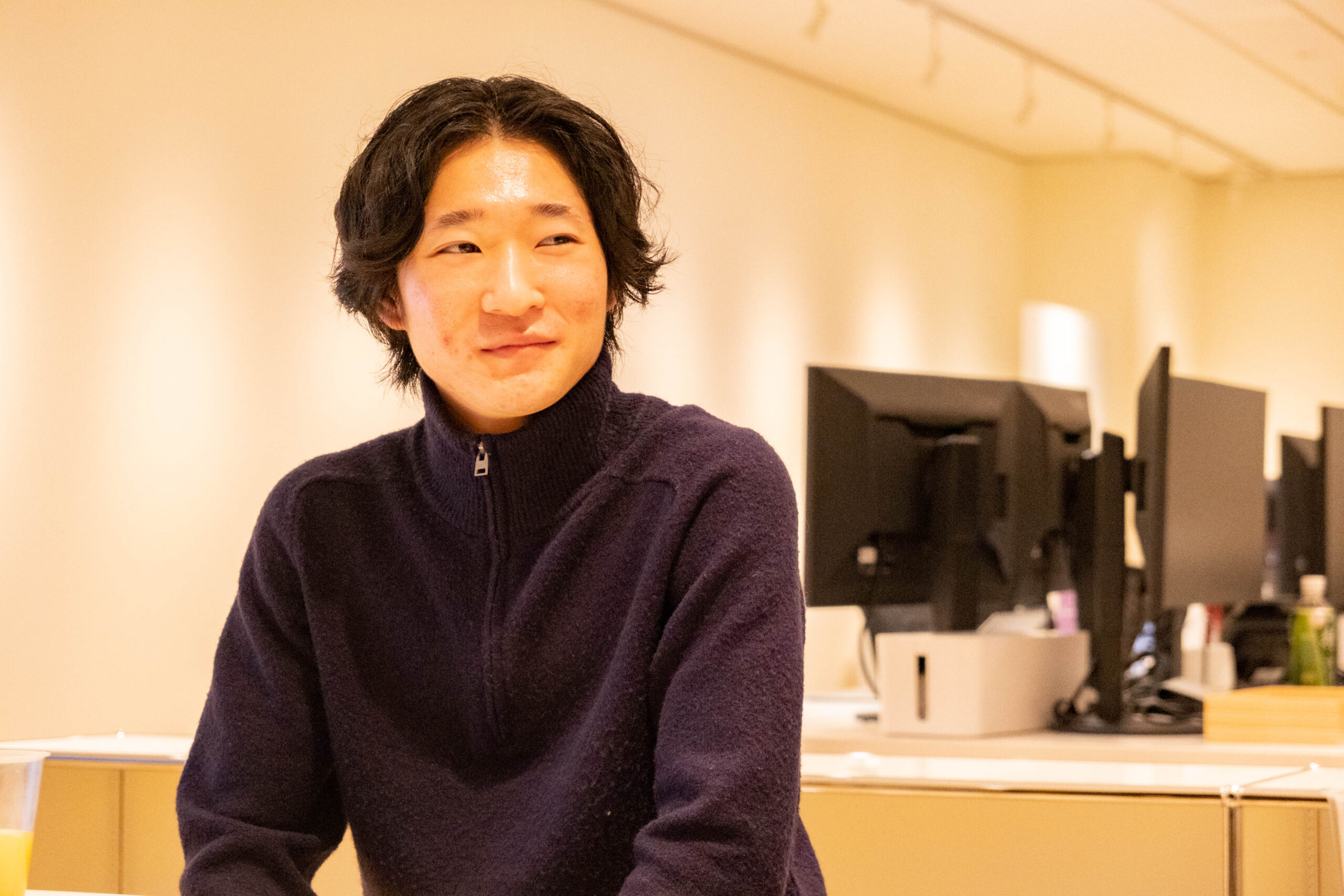
-

G・Yさん:就職活動を見据えてポートフォリオを作成しようと思っています。
そこで、今まで見たなかで好印象だったものや、目に留まるためのコツがあれば教えてください。 -

三浦さん:未経験の方であれば、僕は今現在のデザインの良し悪しなんかはほとんど気にしないです。
それよりどれだけ数を作っているかを見ていますね。
デザイナーもエンジニアもものをつくる仕事、ものづくりが基本。そもそも作ることが好きじゃないと成長もしないし、やっていても本人がつらくなっちゃうんですよね。
だから、「作ることが好きなんだな」と伝わるポートフォリオが好印象です。 -

柴崎さん:僕は現状のデザインの出来よりも、その結果に至ったプロセスが大切だと考えています。
なので、「こう考えた結果、こういう成果になった」と自分が作ったもののこだわりポイントを面接でPRできればいいと思います。
エンジニアとリモートワークの相性は
-

SENDAI INC.:先ほど仙台と東京というキーワードが出ましたが、コロナ渦でリモートワークが一気に加速しましたよね。
「働く場所は関係ない」という考え方も広まってきているようですが、エンジニアの視点から見てこのへんはいかがでしょうか。 -

樋口さん:熟達した方であればフルリモートでも何の問題もないと思いますが、そうでない場合や、分野やスキルが異なる初対面のメンバーが多いプロジェクトの発足時などはちょっと難しいかなと感じます。
その場で「これ教えてもらえますか?」みたいな、ちょっとしたコミュニケーションがないと円滑に進まない場合も多いですね。会話がなくなってストレスを感じる人も多いと聞きます。
-

三浦さん:僕も、クリエイティブを上げるためには週2~3日くらいリアルの場で会う機会を作ることが最低限必要かなと思いますね。
-

SENDAI INC.:フリーランスの立場で、柴崎さんはいかがですか?
-

柴崎さん:僕の場合は、リモートでOK派ですね。
ただその分、コミュニケーションには気を遣っています。
文字ベースのやり取りだとどうしても角が立ったり、うまく伝わらなかったりといった問題が出やすいですから、それがないように努力はしてますね。
どうしてもらちが明かない場合は、会いに行ける距離なら会いに行って話します。 -

SENDAI INC.:作業効率やクオリティを追求するならフルリモートは難しいという考え方がある一方、やり方次第でちゃんと活躍できているという心強いご意見も聞かれましたね。
ありがとうございました。

工夫次第ではあるものの、場所にとらわれずどこでも働けるエンジニアは、これからの時代にフィットした職業であると言えそうです。
デザインやプログラミング、コーディングはあくまで叶えたい目標を達成するための手段であり、それを学ぶこと自体が目標になってはいけないというお話は、ITやエンジニアに限らず心に留めておかねばならないなと感じました。
「より良いものを作り続けるために、常に自分をアップデートし続ける」このマインドがあれば、きっと道は開けるはずです。
Photo:SENDAI INC.編集部
Words:岩崎尚美
※取材時には「黙食」を徹底の上、写真撮影時のみマスクを外していただきました。
PROFILE
大学院在学中にWeb制作を独学で学び、友人4人と合同会社TeamSanta会社を立ち上げる。その後組織変更を行い現在の株式会社AndHAとなる。大手から中小企業様々な業種・業態のホームページ制作を主な業務としている。最近WebGL(Three.js)が好きで日々新しい表現を考えている。バックカントリースノーボードが趣味。
テクニカルディレクター・エンジニア
仙台出身・盛岡育ち。都内・仙台の制作会社にてWEBサイト制作、システム開発、ディレクター等の経験を積んだ後、2020年5月より独立。現在はWEBサイト/WEBアプリケーション開発、テクニカルディレクションに従事するほか、某社のデジタルサイネージシステム開発/運用や、デジタルハリウッドスタジオ仙台でのトレーナーを務めるなど、WEBの技術を通して様々な分野で活動している。
ファストエンジニアリング事業部 事業部長。「株式会社ナナイロ」は「ICTの半歩先へ」の理念のもと、システム・ソフトウェア開発を主としながら、クラフトショップ「STARRY」を出店するなど、B2BからB2Cまで幅広い業務を展開する。自身は物流・各種点検業務をターゲットとした開発を中心に、学習支援アプリ開発、講師派遣やインターンシップの受け入れなど教育支援事業にも取り組んでいる。